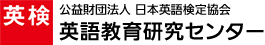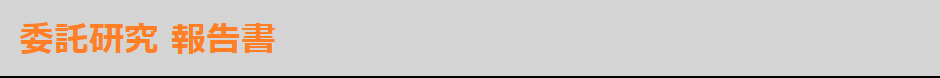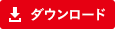英語教員と一般教科教員との協働によるCLIL 実践:設計・授業・研修
委託研究者 池田 真
キーワード:CLIL(内容言語統合型学習)、CLILチームティーチング、CLILプログラム開発、CLIL授業設計、CLIL教材作成、CLIL教員研修、CLIL授業分析、理科(生物)CLIL
【概要】
本報告書は、英語教員と一般教科教員との協働によるCLIL授業を4年間にわたって行った実践校での取組みの記録と考察である。具体的には、日本のCLILの特色、教科横断CLILのカリキュラム設計、実際の授業・教材作りと教室での指導、チームティーチィングの意義と原理、教員研修における授業分析の方法などである。これにより、理論と実践と技法の面から、CLILに対する理解を深め、さらなる実践と研究の発展に資することを意図している。
小学生の英文を「読む力」の育成に効果のある学習プログラム構築を目指して ~文字認識力を効果的に促す「発音指導」の実践と検証~
委託研究代表者 久埜 百合
キーワード:小学校英語
【概要】
2020年度から2023年度までの4年間にわたり、公立小学校にEnglish in Action Online(久埜, 2015)のオンライン英語学習教材を授業に導入し、児童の英語を「読む力」の効果的な文字指導・文字学習の方途について実践研究を重ねてきた。
対象児童は、自分で音を聞く必要があると考える単語や文をクリックして音声を繰り返し聞き、真似て発話するといった音と文字の双方向的な学び方を継続したり、音と文字の関係の気づきを高める文字指導を受けたりした。それらの文字学習が、児童の英語の音声化に何らかの影響を与えるのか、そして、音声化された音と英語を「読むこと」の間には何か関係性があるのか、について事前と事後の音声データと英検Jr.学校版Silver級・Gold級の結果とを比較・検討した。
その結果、公立小学校5年生と6年生との間の文字認識の差や音声処理の差が見られ、さらに、語句の幅広い知識が文字認識の初期段階にあたる単語レベルでの頭音の子音、尾音の子音に対する認知度を高めている可能性も見えてきた。さらに、音声化のスキルの向上が総合的な英語運用能力の育成に影響を及ぼす可能性があることも分析から見取ることができた。このことは、「音声と文字の双方向の文字学習=音声と意味を表す文字の双方を繋ぐ学習」によって示された成果の1つである。
本研究から得られた結果を元に、今後の小学校段階における英語の文字学習の方途について、さらに深めることができると考えている。
改訂学習指導要領(小・中・高)の方向性を考える(2021年度報告)
委託研究代表者 和田 稔
キーワード:学習指導要領
[研究目的・背景と意義]
本報告書は日本英語検定協会・英語教育研究センター委託研究の最終版です。英語教育研究センターの委託研究事業は平成22年(2010)に始まり令和2年(2020)に至る10年間行われました。委託研究事業の目的は「日本の英語教育の発展のため、学校教育のみならず、生涯教育として幼児からシニア層までの日本の英語教育の研究を広く行い、その研究結果を発表し、英語教育の発展に寄与すること」です(『英語教育研究センター 10年の歩み』)。
そして、目標を実現するために、常任審議委員会を組織し、常任審議委員への委託研究、外部研究者への委託研究、英語教育に関する調査研究など様々な研究調査が行われました。当該の研究は常任審議委員による委託研究のひとつです。常任審議委員による委託研究は令和2年(2020)で終了することになりました。本報告書は令和3年(2021)の委託研究の成果の報告です。
委託研究は令和2年(2020)で終了することになりましたが、研究テーマの内容に基づいて研究を1年延長したためです。
改訂学習指導要領(小・中・高)の方向性を考える(2020年度報告)
委託研究代表者 和田 稔
キーワード:学習指導要領
[研究目的・背景と意義]
報告書は2020年度英検・英語教育研究センター委託研究の成果をまとめたものである。研究の目的は平成29年(2016年)度告示の中学校学習指導要領(外国語・英語)(以下、改訂学習指導要領)の理念や言語活動の指導事項を中心に研究グループのメンバーが 1年間研究した成果を共有することであった。2020年度の全体の研究テーマは「改訂学習指導要領(小・中・高)の方向性を考える」であるが、この全体の研究テーマは2019年度の研究テーマの継続であると同時に、過去数年にわたり、研究グループが追及してきた研究テーマの継続でもある。たとえば、2017年度の研究テーマは「改訂学習指導要領 を考える」であり、改訂学習導要領の総則的課題を検討した。2018年度の研究テーマは「改訂学習指導要領を考える ― 改訂学習指導要領(小・中・外国語)の方向性の検討―」であり、総則的課題を踏まえながら、より具体的な課題を研究した。2020年度は研究グループ全体の研究テーマは2019年度のそれを継承しているが、メンバーはさらに焦点 化した研究課題を追究している。このように学習指導要領について研究を積み重ねる根底にはどのような問題意識があるのであろうか。それは学習指導要領のもつ二面性への問題意識であると筆者(和田)は考えている。
日本人児童英語発話の複雑性及び連語使用の発達
—コーパス言語学と動的システム理論の観点から—(2020年度報告)
委託研究者 小池 生夫・鈴木 駿吾
キーワード:第2言語習得
[研究目的・背景と意義]
第二言語習得研究において、発話の複雑性は、正確性や流暢性と同様にスピーキング能力の1つとされている(Suzuki & Kormos, 2020)。 しかし、縦断的研究の不足から、学習者の複雑性における発達順序については十分な研究はなされていない(Lambert & Kormos, 2014)。 スピーキングにおける複雑性には、大きく分けて文法的複雑性と語彙的複雑性の2つに分けられる。文法的複雑性は「特定の文法単位内の情報量」と定義される。 例えば、「1文に含まれる単語数」という観点から分析が可能である。習熟度が上がるほど、1文に多くの語を含めることができ、一度に言語化できる意味情報の多さを示唆する。 語彙的複雑性には、多様さや洗練さなど多くの下位概念が存在するが(Eguchi & Kyle, 2020)、本研究では多様さに焦点を当てる。発話時の多様な語彙使用は、 その学習者の語彙知識がより発達していることを示す。これらの文法的・語彙的複雑性という発話能力に対する見方には、「言語が文法的規則に基づいて産出されるものである」 という前提がある。しかし、言語使用者は、文法規則だけでなく、決まり文句や定型表現(i.e., 用法基盤)を組み合わせて発話を行うという考え方もある(Ellis & Wulff, 2015)。 近年の第二言語習得研究では、「チャンクなどで表現を覚えてから、表現内の文法規則や語彙を習得していくのか」或いは、「文法規則や語彙を習得すると、 それらを応用した表現が定着していくのか」といった文法・語彙・用法の発達順序について注目が集まっている。 本研究では、小池生夫氏の博士論文に用いられた年齢の異なる3人の児童の縦断的コーパスに基づき、実際の英語圏での生活における、文法的・語彙的複雑性の発達に加えて、 用法基盤の考えに根ざす連語使用の変化も縦断的に描写する。
小学校英語の授業の充実を図る現場研修の方法を探る~研究最終年の報告~(2019年度報告)
委託研究者 久埜 百合
キーワード:小学校英語
[研究概要]
本研究は、2017 年 4 月から 2020 年 3 月まで 3 年間にわたる指導者の授業づくりの観点の 変容、そして、子どもの英語の学びに対する「自信度(できる感)」と「英検 Jr.学校版の結 果」の変容をまとめている。その得られた数値の分析により、小学校英語の授業改善のため に現場研修や授業訪問を継続的に行う必要性、及び、新たに「文字を伴うやり取りの授業つ くり」の有効性も見えてきた。また、子どもの「自信度」と「英検 Jr.学校版の結果」には相 関が見られ、自信度の高い子どもは、英検 Jr.学校版での結果も良好であることが 3 年間を通 じて大きく変わらないことも明確となった。 しかし、全体的に 3 年間、文字を「読むこと」に関わる部分についての子どもの「自信度」 が低いままであったが、2 年間継続的に授業改善に取り組んだ連携校の 6 年生の結果には、 大きな違いが見られた。特に顕著な変化は、“できる度 Check”の項目 22・23・24 であり、 2018 年度の連携校の 5 年生の自信度は他よりも一番低いところにあったが、2年後の 2019 年度の 6 年生の時には大きく伸びている。しかし、連携校以外の子どもたちは、大きな変化 が見られないことから、文字を扱った学習の改善は、子どもにとって、英語を「読むこと」に 対する自信を高めることにつながる結果となったと考えている。このことから、今後は、文 字化された単語や文を見ながら進める授業つくりで、子どもの学びを効果的に促す指導改善 の方途に関わる研究が必要であることを示唆していると考えている。
TBLA (Task-Based Language Assessment) に関する研究(2019年度報告)
委託研究者 中村 洋一・法月 健・大友 賢二(元常任審議委員)
キーワード:テスト規準・MRM(Mixture Rasch Model)
[研究概要]
本委託研究は、2011年に端を発し、2011年から2013年までは「言語テストの規準設定」、2014年は「ICT等を活用した評価についての調査・研究」として、言語テストの規準設定についての研究を進め、その方法のひとつとしてMixture Rasch Modelの可能性に注目した。2015年度は、大友・中村・法月による「Mixture Rasch Model による英語能力の規準設定」の研究とし、Mixture Rasch Modelを中心に、規準設定の統計処理法について検討し、その有効性と併せて、限界についても追求し、「該当するその場において、最も適切な規準設定・分割点設定を究明しなければならない」と報告した。2016年の「Mixture Rasch Model による英語能力の規準設定」は、2015年度の研究で明らかになったいくつかの課題について、実際のデータを適応し、MRMの枠組みを使用しているWINMIRAというソフトをして分析した後、Jiao, et al. (2011) の手順によって、 分割点設定の方法を検討した。その結果、さらなる検討課題として、MRM法と潜在ランク理論(LRT)とのより合理的な比較検討、多値データの規準設定、CEFR・TOEFL など複数の規準の比較検討、分割点の利用に応じた規準設定の4つの課題を報告した。2017年は2016年の「Mixture Rasch Model による英語能力の規準設定」の研究を継続し、さらに大きなサイズのデータを用いて、分割点設定に関するいくつかの統計処理を比較検討し、それぞれの利点を規準設定やそのほかの目的に効果的に活用していく取り組みにより、 より洗練された規準設定の統計的解決モデルを構築していくことが望まれると報告した。2018年はこれまでの研究成果と関連させながら、新しい大学入試制度等のとり組みの中で課題となっているperformance assessmentに関わる規準設定の方法論にも目を向けるべく、その出発点をタスク中心のアセスメントに置き、「TBLA(Task-Based Language Assessment)に関する研究」とし、TBLAの文献研究をまとめ、議論の方向性について検討して報告した。以上のような経過の中、2019年度はTBLAの研究を継続すべく、研究を進めていくこととした。
改訂学習指導要領(小・中・高)の方向性を考える(2019年度報告)
常任審議委員 和田 稔
キーワード:学習指導要領
[研究概要]
本報告書は2019年度「英検」英語教育研究センターの委託研究の成果をまとめたものである。研究の中心は平成29年度告示の学習指導要領(中)の言語活動であるが、対象は限定的ではない。そこで、研究テーマは「改訂学習指導要領(小・中・高)の方向性を考える」とした。本報告書では、改訂学習指導要領の基本的理念や具体的な指導の方向性について研究協力者それぞれが 関心を持った論点について1年間かけて研究した成果を論文としてまとめている。
パーマー賞受賞者を対象とする授業力に関する定性的研究
委託研究者 北村 勝朗・常任審議委員 村木 英治
キーワード:パーマー賞
[研究概要]
本研究の目的は,英語教育における優れた授業力とその背後に存在する意識構造を解明することにある。2名の パーマー賞受賞者を対象とし,インタビューおよび刺激再生法(stimulated recall)を用いたインタビューにより調査を行った。質的分析の結果,本研究の対象者において,「自身の内省を通して行動を方向付ける省察性」「学習者の主体的行動を促して着実に英語力を定着させる専心性」社会的文脈の中で学びのしかけを構築する状況性」の3つの要素によって示される意識構造が授業力の背後に存在している点が明らかとなった。
改訂学習指導要領を考える
~改訂学習指導要領(小・中外国語)の方向性の検討~(2018年度報告)
常任審議委員 和田 稔
キーワード:学習指導要領
[研究概要]
本論文集は2018年度 英語教育研究センターの委託研究の研究成果をまとめたものである。 2018年度の研究テーマは改訂学習指導要領(小・中学校外国語)の論点の検討である。 具体的には、論点検討の観点を焦点化し、「改訂学習指導要領の方向性の検討~授業実践における創意工夫を目指す立場から」を研究テーマとして、1年間にわたって議論を積み重ねてきた。本論文集の論文は、その議論の過程で研究グループのメンバー各自それぞれが改訂学習指導要領を授業実践として具体化する観点から、興味を持った論点についてまとめたものである。
Investigating the consequential validity of TEAP: Washback to high school learners of English
お茶の水女子大学 准教授 David Allen 他
キーワード:TEAP・4技能
[研究概要]
This study investigates the consequential validity of the Test of English for Academic Purposes (TEAP) from the perspective of washback on learning. Forty-six high school English learners took the test, revealing that they were mostly at the B1 level in all four skills. All participants completed a pre- and post-test survey examining their learning and test preparation behaviors, and their perceptions of TEAP. In addition, five of these participants were interviewed three times. Positive washback from the test was identified in terms of specific sub-skills (synthesizing ideas in writing, writing about visual data, reading and writing under time-constraints). Moreover, learner perceptions of the test were positive with learners drawing a distinction between the skills tested on TEAP and those tested on traditional entrance exams. Nevertheless, washback was generally restricted due to the limited importance of TEAP for the students and because productive skills were already a focus of their learning.
Mixture Rasch Model による英語能力の規準設定(2)
常任審議委員 大友 賢二
キーワード:テスト規準・MRM(Mixture Rasch Model)
[研究概要]
この研究は、大友賢二(筑波大学名誉教授)、中村洋一(清泉女学院短期大学教授)、法月 健(静岡産業大学教授)による「Mixture Rasch Model による英語能力の規準設定」 (2015)を発展させた、2016年度版である。この規準設定に関しては多くの方法が考えられるが、そのうちでも、正規分布曲線の交点を計算する方法を取り上げている。 この手順に関しては、その方法を、実例を用いながらきわめて詳細に示している。また、MRM(Mixture Rasch Model)とLRT(Latent Rank Theory)との比較検証を行っている。 新しい課題としては、多値データの規準設定も試みている。さらに、CEFR(Common European Framework of Reference)と他のテストとの関連づけに関する課題は、 きわめて興味深いものであるが、その場合の規準設定をどうするのかに関する考察を行なっている。最後に、2017年3月18日に行われた特別講演会「Mixture Rasch Model による英語能力の規準設定」の口頭発表内容(下欄動画)の全てを提示しているのは、きわめて異色である。【この研究に関連する動画】
小学校英語の授業の充実を図る現場研修の方法を探る
中部学院大学 学事顧問 久埜 百合
キーワード:小学校外国語活動・英検Jr.
[研究概要]
小学校英語の現場で、子どもたちの英語習得を深め、コミュニケーション能力を高めるために、指導技術を向上させて授業の改善を図るには、指導者に対してどのようなサポートが必要か、現場研修の内容の検討、指導者が参加可能な学校現場のスケジュールに合わせた研修計画の立て方などを調査したいと考えた。 また、その研修の結果、授業が改善されることがあれば、授業が変わりうるか、そして、子どもたちの学びに、どのような影響がみられるかを、調査したいと考えた。 調査の方法として、今まで6年にわたり使用してきた“できる度Check”で、子どもたちの英語に対する距離感を調査し、その結果と英検Jr. Bronze級のスコアとの相関をもとに、授業記録を分析して、授業改善の方向と研修の在り方とを検討しようと試みた。
大学英語教育の質保証に向けたEAPカリキュラム実態把握調査
一般社団法人大学英語教育学会 EAP調査研究特別委員会
キーワード:EAP
[研究概要]
EAP とはEnglish for Academic Purposes の頭字語で日本語では「学術目的の英語」と訳され ることが多い。このEAP は1960 年代にイギリスの旧植民地での教育を源とするESP (English for Specific Purposes)から発展したもので、海外では1990 年代以降、イギリス、オーストラリア、 ニュージーランド、アジアでは香港、マレーシアなどを中心に広く普及されてきている。 まずはESP である。人は様々なコミュニティを形成し社会生活を送っている。このコミュニテ ィの中では、効率よくやり取りするために、特定の目的、内容、形式を持つコミュニケーション を取り交わしている。ESP はこのコミュニケーションの手段としての英語を指し、「特定の目的の ための英語」「専門英語」「特定の目的のための英語学習教育」などと訳されることが多い。 そのESP はEOP(English for Occupational Purposes、職業目的の英語)とEAP に分かれる。 日本において大学にEAP 教育の必要性が言われ始めたのは15 年ほど前であり、限定的に実施し ているところを耳にはしていたが、実際にEAP を取り入れているところがどの程度あり、その実 情がどうなっているかといった実態を把握する必要があった。 そのようなことを考えていた研究代表者である寺内のところに、賛助会員である公益財団法人 日本英語検定協会(英検)からお声がけをいただき、2014 年から4 年間にも及ぶ研究となったの である。折角のお声がけであるので、個人ではなく一般社団法人大学英語教育学会(JACET)全体 で研究に取り組むべきであると判断し、JACET への委託研究という形を取らせていただいた。 JACET としても賛助会員との関係性を組織として再構築したいと考えていたので、本当にありが たいことであった。 本研究の成果は本編の研究概要と成果などで御覧いただくように、国内外の学会や雑誌 などで発表してきた。しかし、国内外の実態調査の実施とその検証に思いのほか時間がかかり、 新教材やカリキュラム案の提示にまで行きつくことができなかった。これは今後の研究課題とし て次に期待したい。 もちろん、英国、香港、台湾でのEAP 教育の実態調査は日本での調査を行う上でとても示唆に 富むものであった。それらを参考にしてインタビューとアンケートの質問項目を作成し日本での 実態調査に臨んだ。その結果、国内において、そして海外においてさえも、EAP 教育を実践して いる機関が必ずしもそれぞれ目的が同じではなく、実施状況も異なっていることが判明した。 本研究はWeb ではその公開に許諾が得られたもののみを公開することにより、その成果を広く 明らかにしていく。さらに、英国Routledge 社から寺内、田地野が編者となっている(仮題) 『Towards a New Paradigm for English Language Teaching: Current ESP Perspectives in Asia and Beyond』(2020 年刊行予定)の中の1 章に本研究の成果をまとめる予定である。 2 国内外の実態調査でご協力いただいた諸機関(本編記載)に改めて御礼を申し上げたい。
Mixture Rasch Model による英語能力の規準設定
常任審議委員 大友 賢二
キーワード:テスト規準・MRM(Mixture Rasch Model)
[研究概要]
本研究は、2011年度の財団法人日本英語検定協会英語教育センター委託研究に端を発している。2011年度から2013年度までは「言語テストの規準設定」、 2014年度は「ICT等を活用した評価についての調査・研究」、2015年度から現在までは「Mixture Rasch Modelによる英語能力の規準設定」として研究を継続してきた。 6年間の研究成果については、報告書、あるいはPowerPointのスライドで、本ページ上で公開している。また、2017年3月18日の英語検定協会特別講演会にて、 大友賢二研究代表が行った「Mixture Rasch Model による英語能力の規準設定 検討結果と今後の課題」と題した講演でも報告している。 この研究が一貫して検討してきたのは、「規準の設定を客観化するための研究と実践」(大友, 2012, p. 1)である。比較区的広範に及ぶ「言語テストの規準設定」 というテーマのもとで研究を始め、Mixture Rasch Modelの可能性や課題に焦点を絞りながら、現在の研究を展開している。本項では、まず先行研究を再度振り返りつつ、 本研究のこれまでの経過の中から現在の焦点であるMixture Rasch Modelの可能性や課題に関連のある議論を概観し、今後の研究における方向性を見定める論点の整理を行う。それに基づき、実際のテストデータを用いて分析を行い、英語能力の規準設定の方法論を検討する。
教員の学習指導要領の理解の調査
常任審議委員 吉田 研作
キーワード:学習指導要領
[研究概要]
学習指導要領は小学校や中学校、高等学校等で教える内容を定めたものであり、これをもとに教科書等が作成され、現場での教育が日々実践されている。 しかし、教員研修等で非公式に確認した限りでは、一旦教育現場に出ると学習指導要領をきちんと読んだことがないというのが大半を占めているとの報告をよく耳にする。 このようなことも踏まえ、吉田他(2004)以降の英語教員の学習指導要領の内容の理解と実践に関する意識の変容を把握することを本研究の主目的とし、 以下のように研究課題を設定し、アンケート調査を実施しデータを収集し、分析を進めてきた。研究課題1:英語の学習指導要領に明記されている英語教育の理念や目的および言語活動の実践に関して中学校および高等学校の英語教員がどのような意識を持っているか
研究課題2:英語の学習指導要領に明記されている英語教育の理念や目的および言語活動の実践に関する中学校および高等学校の英語教員の意識がどのように変化しているか
研究課題1に関しては、概して多くの教員が英語の学習指導要領に明記されている英語教育の理念や目的および言語活動の実践に関して賛成して、実施していることが判明した。 研究課題2に関しては、経年変化が見られた項目もあれば、ほぼ変化のない項目もあった。 本調査によって、実際の指導の現場において、英語教育の理念や目的がどの程度実践されているか、客観的なデータを示すことが出来た。また、それが実践されない場合、 どのような要因が障壁となっているかについて、多少の示唆を与える分析を進めることが出来た。そして、英語教育における理念と実践を各教員がどのように自分の授業の中で 結びつけていくか、そのために必要な手立ては何か、ということをさまざまな要因ごとに検証していく必要性が示された。
小学校英語:小学生の英語学習能力を踏まえた指導技術向上の方法を探る(2)
中部学院大学 学事顧問 久埜 百合
キーワード:小学校外国語活動・英検Jr.
[研究概要]
2011年以来、研究助成をいただき数年間継続して調査研究をすることができた結果、小学校英語活動 の授業のあり方について、 大変重要と思われるデータを得ることができた。 第一点は、指導者の指導力や英語力だけではなく、指導者の指導観による授業つくりが子どもの習熟に 大きな影響を与えており、 そこに生じている格差が定着していることであった。そして、第二点は、指導 者の英語運用能力や指導力も欠かせないものではあるが、指導者がおかれた教育環境が指導方法の選択の 幅を狭め、それが子どもの習熟度も左右していることが数値としても見えてきたことであった。 この指導観や指導環境によって制約される指導が、子どもたちの英語習熟の格差を 動かないものにして いる状況が続く限り子どもたちの言語習得が改善されないのではないかと考え、その改善の方法を探りた いと願って、2016 年には、別の視点から2つの課題を 取り上げて、研究Aと研究 Bに着手した。【この研究に関連する動画】
早期英語Can-doの研究(児童の学習意欲向上を図る自己評価の効果を探る調査)
中部学院大学 学事顧問 久埜 百合
キーワード:小学校外国語活動・自己評価
[研究概要]
小学校において外国語活動(英語活動)が必修化され、すべての小学生が中学進学前に英語による表現活動を経験するようになったことを踏まえ、2011年度、及び、2012年度は、 “できる度Check”と呼んでいるシートを作成し、子ども自身に記録させることで、子どもたち自身が、「どこまで分かった、できるようになった」と感じていて、 「どんなことをできるようになりたい」と思っているかを調査した。また、対象児童の中で、5、6年生に対して「児童英検」を用い、実際の英語運用能力面での客観的な評価を行った。両年度に得られたデータにより、子どもの自己評価と児童英検の成績とを比較し、“できる度Check”による自己評価の妥当性が検証された。 また、“できる度Check”を用いて子ども自身が学習から得たものについて振り返る機会を与えることによって、期待以上に高い教育的効果があることの示唆を得た。
本年度の研究の目的は、違った学習環境で学ぶ子どもたちの英語習得の実態をさらに詳しく把握することに加えて、現場の指導方法と指導内容について調査を行い、 意図されている指導内容は類似していても指導方法の違いがあれば、それによって生じる学習方法の違いが子どもたちの“英語ができるようになった” と認識する程度に影響があるかを調べ、もしあるとしたら、それがどこまで英語力の獲得と関連しているかを客観的なテストを用いて検証することとした。
言語テストの規準設定(1)
常任審議委員 大友 賢二
キーワード:テスト規準・MRM(Mixture Rasch Model)
[研究概要]
「規準設定」(standard setting) というのは、ごく簡単に言えば、「規準や分割点を設定する手順」ということである。 受験者がある特定の能力水準まで到達したかどうかを決めるのには、どのような手順を踏むのが最も適切であるかということを究明しようとするものである。この報告は、大友・渡部・伊東・藤田・法月による2011年度の研究をまとめたものである。この報告書では、言語テストの規準設定に関連する研究分野を5つ設定し、それぞれの角度からその検討を行っている。
まず、第1の分野は、「規準設定の意味と歴史」(大友賢二・渡部良典)である。ここでは、海外における規準設定法の研究とその動向、 日本における規準設定の応用と実践などが検討されている。
第2の分野は、「内容言語総合型学習(CLIL)における規準設定」(渡部良典)である。特定の目的のための言語・内容重視言語教育からCLILへの統合及び発展などが ここでは検討されている。
第3の分野は、「Can-do statements における規準設定」(伊東祐郎・藤田智子)である。ここでは、日本語能力試験の能力レベルとCan-Do Statements、 英語教育における習熟度レベルとCan-Do Statements などが検討されている。
第4の分野は「テスト理論と規準設定」(藤田智子・法月 健)である。IRTを活用した規準設定、規準設定におけるラッシュモデルの有用性などがここでは検討されている。
そして、第5の分野は、「CEFR・ELPと規準設定」(伊東祐郎・大友賢二)である。ここでは、CEFRにおける6レベルの規準設定の視点、 CEFRと担当テストとの比較:その手段と方法などが論ぜられている。
言語テストの規準設定(2)
常任審議委員 大友 賢二
キーワード:テスト規準・MRM(Mixture Rasch Model)
[研究概要]
「規準設定」(standard setting) というのは、ごく簡単に言えば、「規準や分割点を設定する手順」ということである。 受験者がある特定の能力水準まで到達したかどうかを決めるのには、どのような手順を踏むのが最も適切であるかということを究明しようとするものである。 この研究は、大友・渡部・伊東・藤田・法月による過去1年間の研究を基盤として積み上げられてきている。2012年度の報告書では、それぞれの研究内容は以下の手順で示されている。まず、日本語の論文題目と著者名である。 次の英文のタイトルはその論文の要約を英語で示しているということである。
(1) CITO Variation on the Bookmark Method (大友賢二) A Pilot Survey of the CITO Variation on the Bookmark Method:
(2) “Can-do statements”の比較・研究(伊東祐郎)Comparative studies on practices of Can-do statements :
(3) Can-do statements (CDS) の規準設定(藤田智子)Standard setting for can-do statements :
(4) 受容語彙力を測定するプレイスメントテストにおけるラッシュモデルと潜在ランク理論に基づく規準設定の試行(法月 健)Rasch-LRT Approaches to Setting Standards for a Receptive Vocabulary Size Placement Test:
(5) CLIL における語彙による規準設定(渡部良典)Setting Lexical Standard for CLIL Courses.
言語テストの規準設定(3)
常任審議委員 大友 賢二
キーワード:テスト規準・MRM(Mixture Rasch Model)
[研究概要]
「規準設定」(standard setting) というのは、ごく簡単に言えば、「規準や分割点を設定する手順」ということである。 受験者がある特定の能力水準まで到達したかどうかを決めるのには、どのような手順を踏むのが最も適切であるかということを究明しようとするものである。 この研究は、大友・渡部・伊東・藤田・法月による過去2年間の研究を基盤として積み上げられてきている。2013年度の報告書では、それぞれの研究内容は以下の手順で示されている。まず、日本語の論文題目と著者名である。 次の英文のタイトルはその論文の要約を英語で示しているということである。
(1) CITO Variation on Bookmark Method の一考察 (大友賢二) Investigating the effects of the CITO Variation on the Bookmark Method:
(2) “Can-do statements”の比較・研究 II (伊東祐郎)Comparative studies on practices of Can-do statements II:
(3) Can-do self-checklist の規準設定と妥当性 (藤田智子)Standard setting and validity for can-do self-checklist:
(4) 実用英語検定の級別頻出単語に基づく英語受容語彙力テストの開発と規準設定(法月 健)Setting Standards for Two Versions of a Receptive English Vocabulary Size Test Aligned with Different Grades of Eiken Tests:
(5) 英検は知識測定の道具として使えるかーCLIL の評価規準設定の準備としての固有名詞使用検証(渡部良典) Does EIKEN help measure topical knowledge? Setting Standard for CLIL by identifying the use of proper nouns.
英検型スピーキングテストの量的分析からみた指導法の提言のための研究
清泉女学院短期大学 教授 藪田 由己子
キーワード:スピーキングテスト・指導法
[研究概要]
本研究では、異なる形式のスピーキングテスト(音読、絵描写、応答問題)の間にどのような関係があるか、それらがスピーキングテストの総合点にどのように 寄与しているのかを明らかにすること、受験者のパフォーマンスを質的に分析し、スピーキングテストに効果的な指導は何かを探ることを目指した。結果は、音読は絵描写以外とは全て相関があること、絵描写は他の項目とは相関がみられず、独立因子である可能性が示唆された。 さらに、受験者自身が自分のパフォーマンスを振り返って記入したアンケートでは「質問は理解できたか」、「十分に語ることはできたか」に焦点をあて調査したところ、 応答問題で受験者が「質問を理解できた」ことと教員評価との間にある程度の相関がみられたことから、スピーキング力の前提として、 リスニング力も必要であることがわかった。また、受験者の自己評価と教員評価の関係では、2者の間にある程度の相関を観察できたことから、 受験者の手ごたえは教員評価とそれほどかけ離れていないということも観察された。
【この研究に関連する動画】
日本における英語イマージョン教育の成果と課題
―沖縄アミークス国際学園の事例―
琉球大学 教授 大城 賢
キーワード:イマージョン・小学校外国語活動・英検取得級
[研究概要]
本研究は沖縄アミークス国際学園のイマージョン・プログラムの映像資料、および公益財団法人 日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(英検)の結果をもとに、 イマージョン教育の成果と課題、さらに日本の英語教育への応用を探るものとして研究されたものである。具体的には、沖縄アミークス国際学園の児童・生徒がイマージョン教育の目標として掲げた課題(高い言語能力・コミュニケーション能力の育成、第1言語である日本語の運用力保持、 全教科の教科内容の学齢にふさわしいレベルでの習得など)をどの程度達成できたかを検証することを目的とした。そして、結果、沖縄アミークス国際学園の児童・生徒は高い英語力を 身に付け、日本語力の保持も問題なく、全教科において学齢にふさわしいレベルであることなどが確認された。
【この研究に関連する動画】
ICT等を活用した評価についての調査・研究
常任審議委員 大友 賢二
キーワード:テスト規準・MRM(Mixture Rasch Model)
[研究概要]
このICT等を活用した評価に関する研究の中で最も重視した点は、「規準設定」(standard setting) ということである。それは、ごく簡単に言えば、 「規準や分割点を設定する手順」ということである。受験者がある特定の能力水準まで到達したかどうかを決めるのには、どのような手順を踏むのが最も適切であるかということを 究明しようとするものである。この研究は、大友・渡部・伊東・藤田・法月による過去3年間の研究を基盤として積み上げられてきているものである。2014年度の進捗状況報告では、なぜ、規準設定の方法を究明する必要があるのか?その課題と関連するCEFRとCAN-DO statements、Standard setting 研究結果の流れ、大学入試と段階別表記、 Mixture Rasch Modelの考察、専門雑誌によるMixture Rasch Model 関係の先行研究、21stCentury Skills、語彙能力分析から見たプレイスメントと診断的評価の諸相、等に言及している。 また、最終報告書:Mixture Rasch Model (MRM)の考察と展望では、(1)単純Raschモデルと混合Raschモデル(池田 央)、(2)Standard Setting の視点から(大友賢二)、 (3)21st Century Skills とMRM(中村洋一), (4)統計的解決に基づく分割点設定は可能か(法月 健)、等が論ぜられている。 その状況は、規準設定の客観的手法の一つと考えられるMRM (Mixture Rasch Model)究明の出発点に立ったものである。
日本人児童の第2言語としての英語習得のプロセス研究
常任審議委員 小池 生夫
キーワード:英語習得・コーパス
[研究概要]
本研究は第2言語習得に関するさまざまな研究の中で、特に自然環境の中で3歳ずつ年齢が異なる3人の兄弟妹が英語をゼロからnative speakerのようになっていく過程を定点観測し、 その英語表現構造の成長を分析して陰に働く習得メカニズムを分析報告したものである。1972年に始まり今年2013年までの41年になる長期研究は日本人のSLA研究の嚆矢となり、 研究は継続中である。前期は最初の8年に集中し、後期はおよそ2000年以降からコーパスにタグ付け作業が続いている。前期は手作業により、 後期はコーパス分析を行うのに長期にわたるタグ付け作業が長期間つづいた。前期では出現したほとんどの形態素、統語構造等を正誤分析を行って10例が80%正しく表現された時点で習得したと仮定した。後期では正用表現が出現した数を3か月ごとにまとめて、 各グループ間の表現数の比較をおこなって習得の特徴を分析した。
その結果、3人が無意識に表現したほとんどすべての形態素の習得順序は一定の習得順序に相関があり、統語構造、意味構造でも同様であることが発見された。習得の正用率、 頻度などから英語は使用12か月でほぼ完全に習得される、その後は高原状態を続けることもわかった。習得性は学習への影響を超えた独自のメカニズムが脳内に存在することを 総合的に仮定することになり、大きな発見となった。コーパス分析では習得した語彙を3か月ごとの頻度数分析を行い、どのような語彙が3か月ごとに変化し、取得されるのかを分析し、 その特徴を明らかにした。
【この研究に関連する動画】
言語テストの規準設定における研究
常任審議委員 大友 賢二
キーワード:テスト規準・MRM(Mixture Rasch Model)
[研究概要]
「規準設定」(standard setting)というのは、ごく簡単に言えば、「規準や分割点を設定する手順」ということである。受験者がある特定の能力水準まで到達したかどうかを決めるのには、どのような手順を踏むのが最も適切であるかということを究明しようとするものである。この研究は、大友・渡部・伊東・藤田・法月による過去3年間、大友・池田・村木・中村・法月による過去1年間の研究を基盤として積み上げられてきているものである。この報告書では、(1)中間報告、(2)進捗状況報告、(3)検討結果と今後の課題の3本柱が論ぜられている。その中心は、規準設定の客観的手法の一つと考えられるMRM (Mixture Rasch Model)の究明である。MRMは、ひとことで言えば、Rasch Model と「潜在クラス分析」(latent class analysis)を統合したモデルである。2015年度では、規準設定に関する方法と統計処理、MRMの利点、WINMIRA統計ソフトを使った規準設定手順、受容語彙能力テストの分析などの検討結果などを整理している。今後の課題としてさらに検討を要することは、小グループデータの分析、MRMと他の分析手法との比較検討、言語テストの多値(polyomous)データの活用、また、CEFR・TOEFL・英検などの得点間の比較検討のための「等化」(equating)とその規準設定の手順に関する研究などが考えられている。
CLILにおける内容指導と言語指導の効果的統合法
上智大学 教授 池田 真
キーワード:CLIL(内容言語統合型学習)・英語4技能
[研究概要]
CLIL(内容言語統合型学習)はこの10年間で欧州各国に普及した教育法で、我が国でも小学校から大学までその実践が広まりつつある。 その方法論上の要諦は、教科教育と語学教育の融合にある。そこで本研究では、両者を有機的に統合する具体的指導技法の開発を行った。 用いた方法は、文献や学会参加による理論研究、授業観察に基づく実例収集、教室実践における実用性検証である。その成果として、「内容と言語の効果的統合法」を体系的に整理してモデル化することに成功した。具体的には、内容と言語の統合レベルを、大項目から小項目の順に、 言語スキル(4技能)→学習スキル(4技能のサブスキル)→言語システム(言語知識)→指導的テクニック(細かな指導技術)の4つに分類して明確化した上で、 各レベルでの統合を可能にする「言語意識に基づく指導技法」として、カウンターバランス指導法(内容と言語の行き来)、内容必須言語(必須の語彙と文法の指導)、 学習言語と日常言語(両タイプの意図的使用)、対話型授業(対話による授業運営)、トランスラングエッジング(日英両言語の積極的・計画的活用)の5つを具体的に提示した。
【この研究に関連する動画】
小学校英語:指導技術向上の方法を探る(1)
中部学院大学 学事顧問 久埜 百合
キーワード:小学校外国語活動・英検Jr.
[研究概要]
本調査研究は、2011~2013に行った「早期英語Can-Doの研究(児童の学習意欲向上を図る自己評価の効果を探る調査:久埜百合・相田眞喜子・入江潤)」から得た結果から、 3年間変わらず固定化が進んでしまうのではないかと思われる学校間格差の原因を、授業分析を通して探ろうとしたものである。指導者の指導観、指導技法について大きく隔たりのない国公私立小学校1校ずつを選び、5年生の授業を1年間追跡して、 指導者が目指す指導目標・子どもとのやり取りの回数・使用する語彙の範疇を含め、授業で使われる英語を分析調査した。 子どもたちが英語の授業を受けながら感じていることを踏まえ、英検Jr. Gold級を受験させて、その結果と授業の成果とを照合してみると、それぞれの指導者がおかれている教育環境が、 指導技術以上にその結果に大きな影響を及ぼしていることが分かった。この教育環境を規定する条件を改善することが格差の解消につながるともいえる。 これは教育界全体にもかかわる大きな課題であることも明らかになった。学校内の学習環境を整えることで、どこまで子どもの習得を高めることができるか、 それが小学校英語の指針となり得るかが次の課題である。
【この研究に関連する動画】
協同調整学習から自己調整学習へ
グローバル化時代に対応した英語ライティング能力育成法の基礎的研究
関西大学 教授 竹内 理
キーワード:ライティング能力
[研究概要]
L2学習における協働の役割については、近年その重要性が盛んに指摘されるようになっている。しかしながら、ライティングの学習においては利用がまだ限定的であり、 Collaborative Writing(CW)活動が学習過程にどのような利点をもたらし、どのような変化を引き起こすのかなど、まだ十分に解明されていない。そこで本研究では、Storch(2013)の提唱する枠組みと、Swain & Lapkin(1998)のLanguage Related Episode(LRE)の概念を利用しながら、 1) CW の過程において、 どのような学習方略が利用されるのか 2) CWはLREの出現とその性質に対してどのような影響を与えるのか 3) CWは学習者の態度にどのような影響を与えるのか の3課題の解明を試みた。 その結果、CW活動を行っても、様々な形態が出現し、必ずしも協働が実現できるかは保証できないことがわかった。協働が生じにくくなる理由としては、 参加者の自信の欠如や相手の体面への配慮、それに時間的制約や成績付与システムのあり方などが関係していることがわかった。またCW活動の中では、 協働の度合いが増すほど方略の組み合わせ使用が増えることや、LREの中での焦点の置き方が「論理の流れ」にシフトすること、さらには CW活動自体への態度も好転することなども示された。
【この研究に関連する動画】
大学英語教育の質保証に向けたEAPカリキュラム実態把握調査
JACET会長 高千穂大学 教授 寺内 一
キーワード:学術目的の英語(English for Academic Purposes: EAP)
[研究概要]
本研究は,日本の大学で実施されている学術目的の英語(English for Academic Purposes: EAP)教育を対象とし,カリキュラムの現状と課題を把握することを目的としている。 まず,日本のEAP教育への示唆を得るため,英国と香港で実施されているEAPカリキュラムの実態調査を行い,その結果に基づき国内大学に対する調査項目を検討した。 国内大学では4大学を対象に質問紙およびインタビュー調査を実施した。主な調査結果は以下の3つである。1)今回調査した大学は,独自にEAPカリキュラムを開発・実施しているが, 主に一般学術目的の英語(English for General Academic Purposes: EGAP)カリキュラムを意味している。2)他国では英語教員と専門分野教員の協力によるニーズ分析と教材開発など, 組織的連携が実践されているが,この連携は1校を除き確認されなかった。3)各大学で質保証に向けて様々な取り組みが継続的に行われているものの, プログラム評価の実施は一部の大学にとどまった。調査結果から,日本の大学におけるEAPカリキュラムは,教育内容と運営体制の点で,発展途上にあると推測された。2016年度から,公益財団法人日本英語検定協会からの委託研究として,大学英語教育学会が大規模調査を行うことになっている。
【この研究に関連する動画】
小中を連携させる効果的な文字指導に関する研究
長崎大学 教授 中村 典生
キーワード:小中連携・小学校外国語活動
[研究概要]
2014年10月に示された「グローバル化に対応した英語教育改革の五つの提言」の中には、中学校において音声から文字への移行が円滑に行われていない場合が見られる、 という現状が示されており、また「高学年では身近なことについて基本的な表現によって「聞く」「話す」に加え、 積極的に「読む」「書く」の態度の育成を含めたコミュニケーション能力の基礎を養う」という文言が盛り込まれている。今後小学校でも文字を扱うこととなれば、 どのように扱うか、ということは大変重要な問題となる。本研究では以上をふまえ、まず文字指導の議論を整理し、何が課題であるかを洗い出す。続いて、その課題を踏まえて考案した「文字指導(活動)例報告シート」を用いて、 全国で行われている文字指導に関する情報を収集する。このシートでは、活動の具体例の記述箇所に加え、様々な分類肢が設けられているので、それを利用して文字指導の分類・分析をすることができる。この分類と分析をもとに、今後の小学校における文字指導のしかるべき方向性について示すことが本研究の目的である。具体的には、いかにして文字を導入し、指導を展開していくのが効果的か、という「文字指導の階段」の作成を試みる。
【この研究に関連する動画】