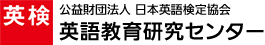書籍名:Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, qualitative and mixed methodologies 著者名:Dörnyei, Z. 出版社:Oxford University Press |
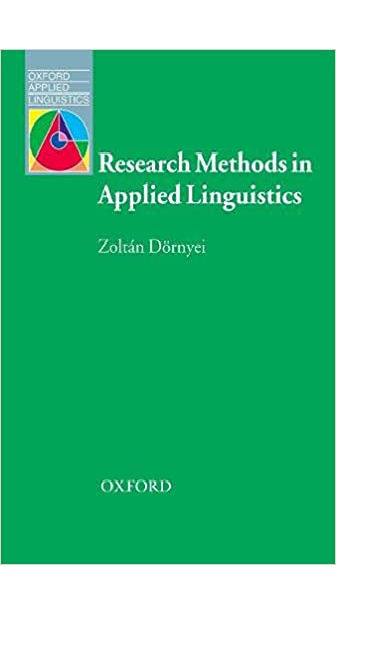 |
おすすめの理由:和泉 伸一 委員
本書は、量的研究、質的研究、そして両者を統合して行う混合研究法についてわかりやすく書かれており、応用言語学の研究入門書として定評が高い本である。研究の意義や方法についてある程度わかっている人にも、ほとんど知らない初心者にとっても、有益な本であり、研究の生産者(researcher)という立場はもちろんのこと、消費者(reader)の立場でも、知っておくべき情報が満載された書籍である。 おすすめの理由:竹内 理 委員 「英語で」研究デザインや分析手法(量・質・混合法)について学びたい人たち向けの書籍。質問紙調査を指向する方は、本書のあとに、同一著者によるQuestionnaire in second language research(邦訳『外国語教育学のための質問紙調査入門』松柏社)も読むと、一段と理解が深まるはず。 |
書籍名:はじめての英語教育研究 著者名:浦野 研, 亘理 陽一, 田中 武夫, 藤田 卓郎, 髙木 亜希子,酒井 英樹 出版社:大修館書店 |
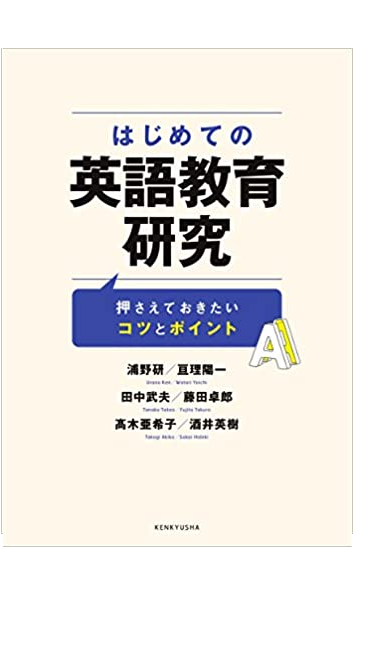 |
おすすめの理由:竹内 理 委員 研究テーマを決め、データを集めるところからスタートして、成果を発表するところまで、一連の流れを具体的な例とともに平易に解説している。学部学生の卒論から、現場ではじめて研究をする人までが使える入門期のおすすめの一冊。 おすすめの理由:西垣 知佳子 委員 「これから英語教育研究をはじめよう」「英語教育研究について基礎から学びたい」と考えている方におすすめの本です。「研究テーマの設定」から「研究成果の公表」まで,一連の研究過程を順序立てて解説しています。また,研究を進める上で押さえるべきポイントとコツがわかりやすいので,学部や大学院のゼミで指定図書となっていることも多い本です。 |
書籍名:SOFT CLIL AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING: UNDERSTANDING JAPANESE POLICY, PRACTICE AND IMPLICATIONS 著者名:Ikeda, Izumi, Watanabe, Pinner, & Davis, R 出版社:Routledge Series in Language and Content Integrated Teaching & Plurilingual Education |
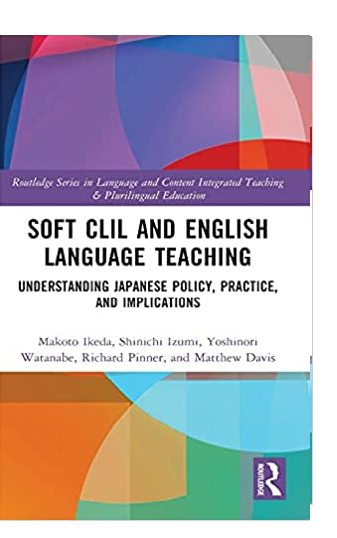 |
おすすめの理由:和泉 伸一 委員 CLIL(Content and Language Integrated Learning)は世界ではもちろんのこと、現在、日本国内でも小学校から大学に至るまで広がりを見せている。その試みを世界に対して発信していこうとするのが本書の目的となっている。研究方法に特化した本ではないが、CLILについて教育実践との関連で理解を深めて研究に役立てたいと考える読者にとっておすすめの書である。最終章では、これからCLILを発展させていくために必要と考えられる研究提案がなされている。 |
書籍名:「フォーカス・オン・フォーム」を取り入れた新しい英語教育 著者名:和泉 伸一 出版社:大修館書店 |
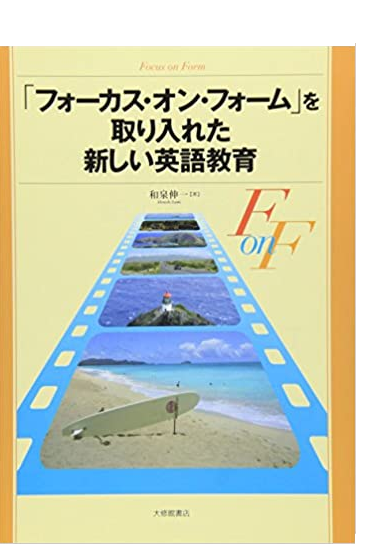 |
おすすめの理由:和泉 伸一 委員 本書は、コミュニケーションを主体とした英語授業の中で、文法などの形式指導をどのように織り交ぜて、バランスの取れた英語能力の獲得を目指していけるかを論じた書である。研究方法に特化した本ではないが、関連する先行研究を上記の目的のために整理して紹介してあり、日本の英語授業のコンテクストでどのような研究課題が存在し、それにどう迫っていったらいいのか、その背景知識と研究方向を見定める上で有益となる書である。 |
書籍名:Scoring Second Language Spoken and Written Performance: Issues, Options and Directions. 著者名:Knoch, U., Fairbairn, J., & Jin, Y. 出版社:Equinox |
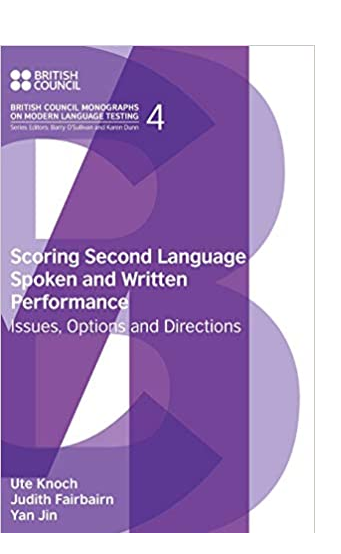 |
おすすめの理由:小泉 利恵 元委員 スピーキングやライティングのテストをどのように採点するか、またその過程でどのような要素が関わっているかなど、採点に関する先行研究が詳細にまとめられており、今後取り組むべき課題が見えやすくなります。例えば、採点はどのようなルーブリックを使って、どのような方法で行うのがよいか、採点を容易にするテクノロジーにはどのようなものがあるか等、多彩で参考になる研究が既にこれほどあるのかと驚かれると思います。 |
書籍名:実例でわかる 英語スピーキングテスト作成ガイド 著者名:小泉利恵(編著) 出版社:大修館書店 |
 |
おすすめの理由:小泉 利恵 元委員 添削編と実例編で、小中高大におけるスピーキングテストの具体例を(ビデオ付きで)、理論編では、スピーキングテストの作成、実施、採点、フィードバックについての考え方や、テストを年間を通して無理なく運用する方法を詳細に学ぶことができます。4技能のテストを扱った『実例でわかる 英語テスト作成ガイド』とともに、テストに関する研究の種を拾える本です。 |
書籍名:英語教育論文執筆ガイドブック:ジャーナル掲載に向けたコツとヒント 著者名:廣森友人(編著) 出版社:大修館書店 |
 |
おすすめの理由:小泉 利恵 元委員 研究を国内外のジャーナルに投稿したり、査読結果に対応したりする際に、どのような点に注意したらよいかがよくわかる本です。American Psychological Associationの執筆マニュアル(第7版)に沿って、量的研究や質的研究など、研究のタイプごとに執筆時の留意点が詳しく書かれています。様々な立場の研究者による論文執筆の経験談が書かれたコラムも、研究への意欲を高めるのに役立ちます。 |
書籍名:テスティングの基礎理論 著者名:野口裕之・大隅敦子 出版社:研究社 |
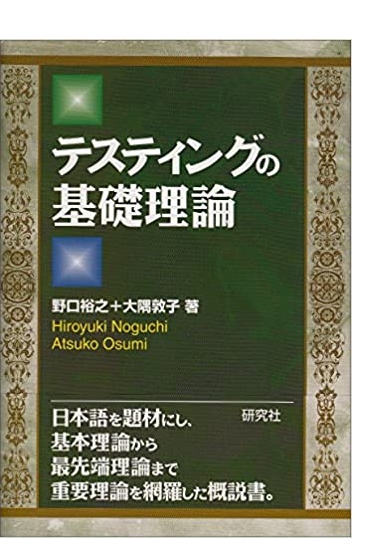 |
おすすめの理由:斉田 智里 委員 外国語教育におけるテスト理論そのものに焦点をあてた数少ない優れた解説書です。英語能力テストに関する研究を行う上で、一度はきちんと学んでおきたい理論です。同著者の『統計で転ばぬ先の杖』(2021年、ひつじ書房)も、統計分析を行い報告書をまとめる上で一読の価値があります。 |
書籍名:実践的英語科教育法 著者名:酒井英樹・廣森友人・吉田達弘(編著) 出版社:大修館書店 |
||
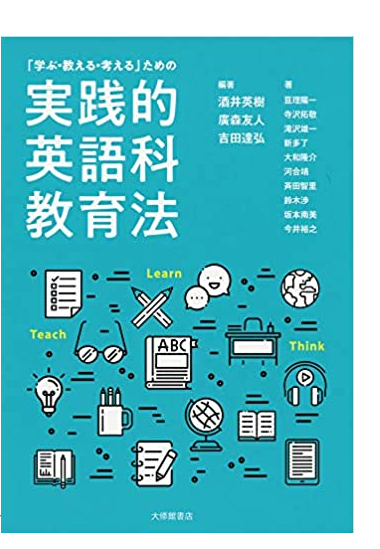 |
おすすめの理由:斉田 智里 委員 英語科教育の全体像を「英語・教育政策編」、「学習・学習者要因編」、「指導・指導者資質編」の3本柱で再構築し、読者とのインタラクションを重視しながら、深い論考と豊富な情報が提供されています。実践をもとにした研究テーマを考える上で有益な一冊といえるでしょう。 |
書籍名:英語教育学の今-理論と実践の統合 (全国英語教育学会第40回研究大会記念特別誌) 著者名:全国英語教育学会発行 出版社:全国英語教育学会発行 |
||
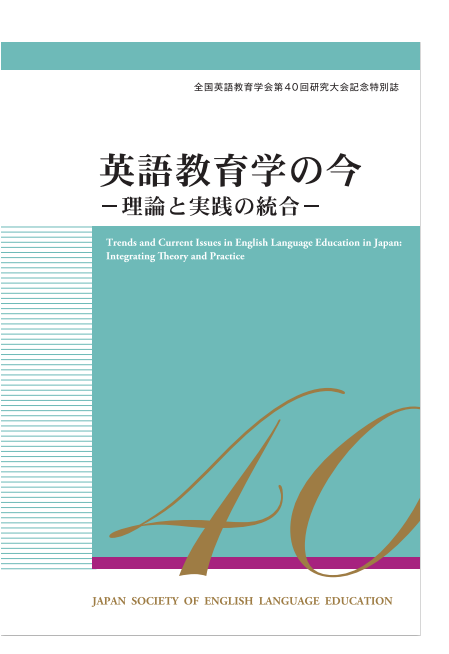 |
おすすめの理由:斉田 智里 委員 英語教育の最新の研究動向と実践例が第一線の研究者たちにより分野ごとにコンパクトにまとめられています。研究を始めてみたいが、何から手を付けていいかわからないときまずは手にしてほしい一冊です。全国英語教育学会ウェブサイトより誰でもダウンロード可能です。 |
書籍名:外国語教育研究ハンドブック(改訂版) 著者名:竹内 理, 水本 篤 出版社:松柏社 |
||
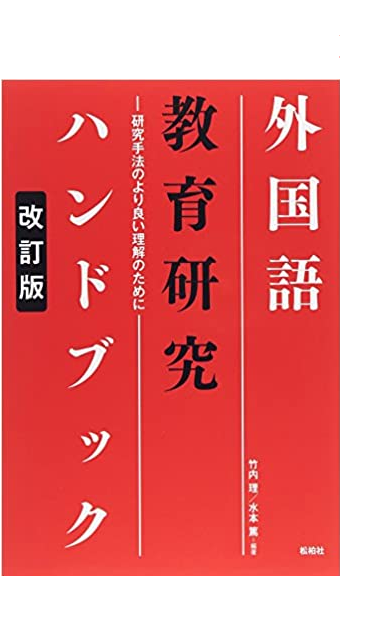 |
おすすめの理由:竹内 理 委員 外国語教育研究の基本から発展までを、量・質の両側面から網羅的にカバーしている。平易な文体のため通読するのもよし、索引が充実しているので、傍らに置きレファレンス的に利用するのもよし。ウエッブ上のコンパニオンサイトを利用すれば、簡単な統計処理も無料で可能。 おすすめの理由:鈴木 渉 委員 本書は、第二言語に関する研究で使われている量的・質的な研究が紹介されており、これから研究を始めようとする方に向いています。2012年の初版から、改定版を経て、増補版に至っており、多くの英語教育関係者に読まれています。コンパニオン・ウェブサイトでは、本書で使用されたデータをダウンロードし、エクセル・SPSS・R等を使って、ステップバイステップで分析することができ、体験的に理解が深まります。 |
書籍名:Writing for Academic Purposes-英作文を卒業して英語論文を書く 著者名:田地野彰、ティム スチュアート・デビッド ダルスキー(編) 出版社:ひつじ書房 |
||
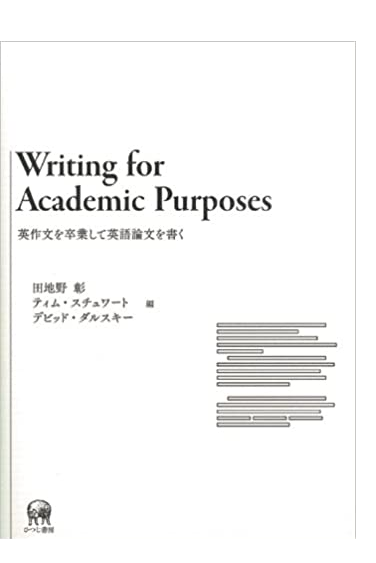 |
おすすめの理由:寺内 一 委員 本書は読み進めているうちに論文のスタイルに自然に慣れることができることが大きな特長である。英作文とアカデミックライティングの違いを意識しながら英語学術論文の構造を理解することになる。読者がどのような専門分野に進もうとも、アカデミックライティングの基本を身につけるには絶好の書物であると言える。 |
書籍名:ことばのデータサイエンス 著者名:小林雄一郎 出版社:朝倉書店 |
||
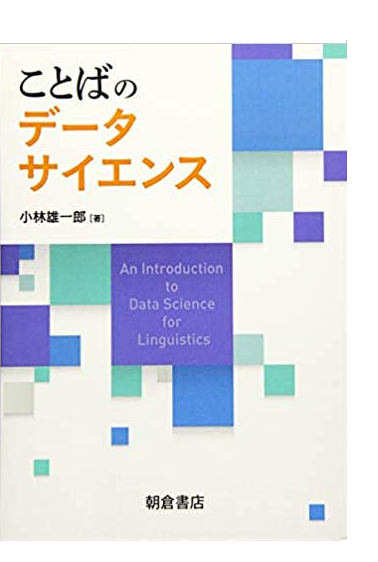 |
おすすめの理由:西垣 知佳子 委員 「言語を計量的に分析したい」と考えている方におすすめの入門書です。コンピュータや統計学を用いて行う言語研究の方法を実際の言語データを用いて解説しています。図・表が多くイメージがつかみやすく,初心者にもわかりやすい言葉で書かれています。本書を通して,この分野の専門用語も学べます。英語教育に関わる言語データを分析する際に役立つ1冊です。 |
書籍名:教育を読み解くデータサイエンス:データ収集と分析の論理 著者名:耳塚寛明 (監修), 中西啓喜 (編著) 出版社:ミネルヴァ書房 |
||
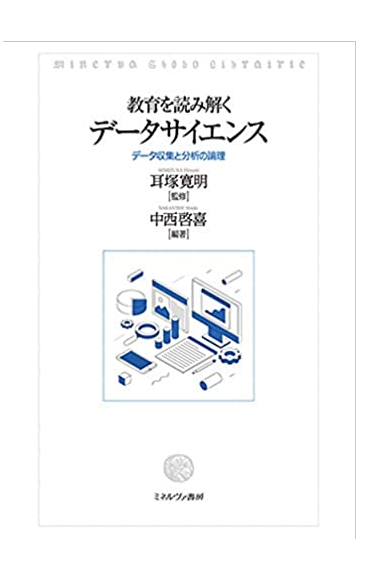 |
おすすめの理由:西垣 知佳子 委員 データサイエンスの本をご紹介します。2021年5月に出版された図書で,教育に関連するデータサイエンスを扱っています。本のタイトルのとおり,教育関連の統計的なデータを読むことを目的としています。さらに,リサーチ・クエッションの立て方,データの集め方,統計の基礎,教育データの読み方,教育データの分析手法,研究倫理の重要性等,研究の進め方についても学べます。 |
書籍名:Second language research: Methodology and design 著者名:Mackey, A., & Gass, S. 出版社:Routledge. |
||
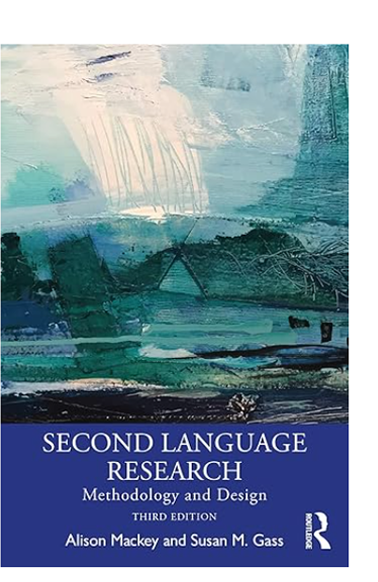 |
おすすめの理由:鈴木 渉 委員 本書は、第二言語に関する研究事例が豊富に紹介されており、これから研究を始めようとする方に適しています。本書を読むことで、倫理書類を準備する、研究を導く仮説を生成する、データ収集の方法を選択しデザインする、妥当性や信頼性について理解する、E-primeやNVivoなどの研究ツールを使う、研究レポートを作成する、など様々なことができるようになります。 |
書籍名:心理学研究法-心を見つめる科学のまなざし【補訂版】 著者名:高野陽太郎・岡隆(編) 出版社:有斐閣アルマ |
||
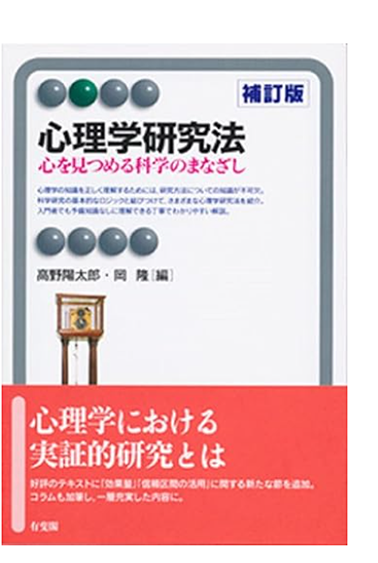 |
おすすめの理由:鈴木 渉 委員 本書は、心理学の研究方法を解説した本ですが、心理学の予備的な知識は必要なく、第二言語に関する研究をこれから行う方に、非常に役立つ内容になっています。特に、実験的研究と観察的研究について詳しく分かりやすく解説されているのが特徴です。英語教育研究も、学習者や教師の心の働きを研究対象にしていることから、本書を通して、代表的な研究方法について、広い知識と深い理解を得ることができるでしょう。 |