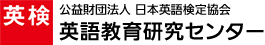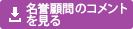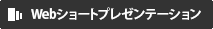研究部門 Ⅰ 英語能力テストに関する研究
英語学習者エンゲージメントに関する文脈的モデルの妥当性検証
東京都/明治大学大学院 在籍 樫村 祐志
▼研究概要
本研究は,英語学習者におけるエンゲージメントに関する文脈的モデルの妥当性検証を行うことを目的とする実証研究である。関東の中学校,高等学校,大学に通う英語学習者753名を対象に,エンゲージメント,および,その先行要因(心理的欲求,動機づけ)とアウトカム(習熟度)に関する質問紙調査を実施した。予備的分析として因子構造を確認したのち,記述統計にて全体傾向を把握した。次に,多母集団モデルによる共分散構造分析を行った結果,英語学習における心理的欲求・動機づけ・エンゲージメント・習熟度に関する文脈的モデルが妥当であることが示された。最後に,心理ネットワーク分析の結果,変数同士がポジティブに関連しあったシステムを形成しており,中でも自律的動機づけの3変数(内発的,統合的,同一視的)が中心的な役割を果たしていることが明らかになった。