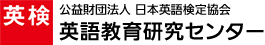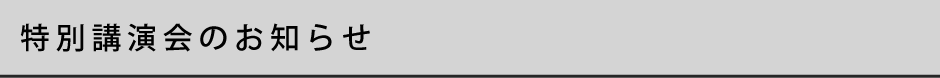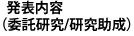公益財団法人 日本英語検定協会 英語教育研究センターは、2010年の創設以来、日本を代表する研究者・教育者の先生方に研究を依頼し、多くの優れた成果を蓄積して参りました。
今回、英語教育研究センター常任審議委員を中心に、委託研究者、研究助成入選者、協会内研究者を含め、研究成果の発表会を開催いたします。
【開催日時】 2017年3月18日(土) 13:00~18:00
懇親会 18:00~20:00
【会場】 アルカディア市ヶ谷 6階 霧島(東京都千代田区)
【対象】 小学校・中学校・高等学校・大学の教職員の方、大学生・大学院生、英語教育に関心のある方
【定員】 100名(先着順)
【参加費】 無料(懇親会にご参加の方は2,000円)
【お問合せ】 公益財団法人 日本英語検定協会 英語教育研究センター center@eiken.or.jp
特別講演会は終了いたしました。たくさんのご来場ありがとうございました。
タイムテーブル等の詳細はこちらのPDFをご覧ください。
大友 賢二
筑波大学 名誉教授
「Mixture Rasch Model による英語能力の規準設定検討結果と今後の課題」
【概要】
「規準設定」(standard setting)というのは、ごく簡単に言えば、「規準や分割点を設定する手順」ということである。受験者が、ある特定の能力水準まで到達したかどうかを決めるのには、どのような手順を踏むのが最も適切であるかということを究明しようとするものである。
その中心は、規準設定の客観的手法の一つと考えられる「混合ラッシュモデル(Mixture Rasch Model:MRM)」の研究である。MRMは、一言で言えば、「ラッシュモデルと潜在クラスモデル」を統合したモデルである。規準設定に関する方法、MRMの利点、ソフト:WINMIRAの利用などの検討結果を報告する。
また、今後の課題として、MRM と他の分析手法との比較、多値(polytomous)データの利用、CEFR やTOEFLなど複数の規準の比較検討、分割点の利用に応じた規準設定などを取り上げて、その問題点を検討することとする。
【この発表に関する論文】
【この発表の動画】
長 勝彦
一般財団法人 語学教育研究所 参与
「授業に於ける教師、生徒の英語発話量と質についての調査研究」
【概要】
「英語の授業は英語で」と多くの英語教師は英語で授業を行おうと取り組んでいる。昨年、根岸雅史教授(東京外国語大)が「中高の英語指導に関する実態調査2015」を発表した。その調査結果によると、授業で英語を半分以上使っている割合は、中学校6割、高校5割弱であった。具体的な英語使用場面は、「生徒への指示」「褒め・励まし」「生徒とのQ&A」などが7割を超えており、それを受けて根岸雅史教授は「授業中での英語使用のスタートに過ぎない。」とコメントしている。そもそもこれらの調査研究は、アンケートに基づく調査研究結果であり、実際の英語使用量はより少ない可能性がある。
これまで、授業における英語の使用量を実測し分析した調査研究は未だ発表されていない。本研究は、共同研究者、佐藤剛(弘前大)、鈴木悟(都立両国高校附属中)、寿原友里子(三宿中)、森沢俊彦(西池袋中)と共に、パーマー賞受賞者の授業、全英連大会公開授業者の授業という、実際の授業の映像を時間を掛けて調べ、授業と生徒の授業内での英語発話量と英語使用場面の分析を行った。その結果を基に「英語の授業は英語で」の授業の在るべき目標を提示して、英語教師各自が自身の授業評価が日常的に可能である事を提言するものである。
【この発表の動画】
小池 生夫
慶應義塾大学 名誉教授
「日本人児童の第2言語としての英語習得のプロセス研究」
【概要】
半世紀近くの第2言語習得研究の歴史の初期に、形態素習得に被検者共通の順序性があることが発見された時期があったが、その後この種の研究は関心が低くなっている。そこに再度光を当てて考察してみたい。
発表者の長期資料分析の対象は約3歳づつ異なる3人の兄弟妹の英語環境でのデータを分析すると、彼らの英語習得の特徴に違いがある部分もあるが、形態素構造、文構造、文法的意味構造の習得の類似性がかなりの範囲に認められる。習得に順序があるのはなぜか。どのようなものか。習得のメカニズムが複雑に働くが、異なった形態素間と文の間の習得のorder とsequenceの問題、意味と形態の関係、脳の自律的働きと習得の関係、形態素間の習得順序の定まる理由など、さまざまな問題を絞って述べてみたい。
【この発表に関する論文】
「日本人児童の第2言語としての英語習得のプロセス研究 」(PDF)
【この発表の動画】
村木 英治
東北大学名誉教授
「Samejimaの連続項目反応モデルのパラメータのMCMC推定法と質問紙法への応用」
【概要】
準備中
【この発表の動画】
和田 稔
明海大学名誉教授
「学習指導要領の『拘束性』と『創意・工夫』を考える。~現行学習指導要領を対象として~」
【概要】
学習指導要領は学校教育で全国的に一定の教育水準を確保するため、法令に基づいて国が定めた教育課程の基準であり、各学校はこれに従わなければならないものであるが、他方、学習指導要領に示された教科の目標・内容等は大綱的なものであり、学校や教師の創意工夫を加えた学習指導が期待されている。学習指導要領における「拘束性」(「従わなければならない」)と「教師の創意工夫」との関係は微妙なバランスのうえに成り立っている。
現行学習指導要領の核となる「コンセプト」は何か、その「コンセプト」を教師がどのように受け止めて授業を作り上げるか(「創意・工夫するか」)、を研究テーマとして2015年度、2016年度、2017年度3年間調査・研究をする。
本年度は教科書が学習指導要領をどのように受け止めて作成されているか(「創意・工夫をしているか)、を分析している。何故、教科書を分析するのか。日本の学校教育では、教科書が「教師の創意工夫」を先導している側面があるからである。その分析の一端を開示する。
【この発表の動画】
池田 真
上智大学 教授
「CLILにおけるトランスラングエッジング活用のモデル構築」
【概要】
CLIL (Content and Language Integrated Learning) とは、外国語(主に英語)で内容(一般教科や科目横断トピック)を高度な思考力を用いてアクティブに学ぶ教育法である。
タスクベースの内容学習を通してオーセンティックなインプット、アウトプット、インターラクションの機会が多く与えられることで、英語運用力が高まるとされている。そのため、使用言語は英語に限るのが原則であるが、ここ数年のトランスラングエッジング (translanguaging) という概念の広まりにより、授業における積極的母語活用が議論されるようになった。
そこで本発表では、文献研究や欧州での授業観察に基づき、その概念や機能を整理した上で定義付けを行い、CLILにおけるトランスラングエッジング活用の原理とモデルおよび実践法を具体的に提示する。発表の最後には、この分野で期待される今後の研究の方向性にも言及したい。
【この発表に関する論文】
「CLILにおける内容指導と言語指導の効果的統合法」(PDF)
【この発表の動画】
野上 泉
茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 教諭
「高校の英作文の授業での生徒同士のフィードバック活動の効果」
【概要】
日本の高等学校での英語教育において,生徒がパラグラフ単位で英文を書く機会は限られており,パラグラフ単位で書く能力の育成が遅れていた。
近年,この傾向に変化が見られる。高等学校学習指導要領において,生徒がまとまりのある文章を書けるようになることが求められ(文部科学省,2010),ほとんどの教科書でパラグラフ単位でのライティングを扱うようになった。また,大学入試においてもパラグラフ単位での英作文を課す大学が増えており,英検2級でも2016年度よりライティング・テストが導入された。
しかしながら,まとまりのある文章を書く能力は現状ではまだ十分に養われているとは言い難い。文部科学省が2015年に行った調査によると,調査を受けた高校3年生約7万人のうち、約60%の生徒が,高校の授業で自分の意見を英語で書く機会がほとんど,または全くなかったと回答した。
このように日本の高等学校の英語教育においてはパラグラフ単位でまとまりのある英作文を書くための指導が十分根付いておらず,効果的な指導方法を探っていくことが必要である。
本研究では,まとまりのある文章を書くための指導の一つの方法として,文章のまとまりに焦点をあてた生徒同士でのフィードバック活動を授業に取り入れ,その活動が生徒の作文を書く力にどのように影響を与えるかを検証した。
【この発表に関する論文】
「高校生の英作文における「文章のまとまり」に焦点をあてたピア・フィードバック活動の効果」(PDF)
【この発表の動画】
仲村 圭太
公益財団法人 日本英語検定協会 制作部研究開発課
「英検・TEAPのリーディング語彙に関する研究」
【概要】
日本の大学入試は高大接続を焦点に改革が進みつつある。特に英語に関してはグローバル人材の育成の観点から中央教育審議会高大接続部会においても大学入試における外部試験の活用が検討されている。またテスティング及び言語テスティングの観点(植野他2008, Bachman and Palmer, 2000)から、試験において出題するタスクの設計や難易度等に関する情報を利害関係者と共有し、良い波及効果がもたらせるようにすることが望ましいとされている。
テストの設計において語彙は文法、表現、グラフなどタスク設計を構成する一つの側面ではあるが、特にリーディングテストにおいては問題冊子上に印字された英文テキストに含まれる語彙の頻度とその割合が英文の理解に大きな影響を与えると考えられる(Nation,2006)。本発表においては大学入試において外部資格・検定試験として活用されているTEAP、及び実用英語技能検定(英検)のリーディング部分で扱われている語彙の側面に焦点を当てて、調査を行った。
複数セットから得られたデータをRange with GSL/AWL及びRange with BNCまたMetametrics社が開発したLexile指標を用いて分析を行った。本発表においては上記方法によって得られた結果を報告する。
【この発表の動画】