金森強
文教大学 教育学部教授
専門は英語教育、音声学、早期英語教育。日本児童英語教育学会理事、小学校英語教育学会理事。小学校~高校のデモ授業と教員研修で全国を飛び回る。講演テーマは、小中・中高連携を意識した指導、統合的な活動の開発・評価、Can-Doリスト作成の在り方、歌・ゲームを利用した英語指導など。著書多数。
8月2日に開催された「語学教育メディア学会(LET)」の全国大会(於:福岡大学)で佐藤学先生(学習院大学)の基調講演:「言語リテラシー教育の再検討―言葉としての英語の学びへ―」を聞く機会を得た。氏の考える「言語リテラシー教育」における「リテラシー」とは、単に「識字能力」の育成を表すのではなく、教養教育・リベラルアーツを通した人間教育までの広がりを持つとするものである。
Literacyはletterから派生してできた単語であるが、現在では、古典的な「識字能力」だけではなく、「自らの力で情報を得、さらにその情報を利用・活用する力」とする新たな意味さえも生まれてきている。また、ユネスコにおいては、読み書きを通してさまざまなことを理解したり、創造したり、関わったりする能力。さらに、人間が自らの目標や目的を成し遂げるために知識や技能を高めたり、共同体やより広い社会に対して貢献し続けたりすることを可能にさせる能力として用いられているようである。
「グローバル人材育成を目指す外国語教育」の実践を考えると、佐藤氏が指摘する広い意味における「言語リテラシー教育」こそが望まれるところであり、この視点を外国語教育に組み入れることなしには、充実した外国語教育の改革は起こり得ないように思える。
「英語教育の在り方に関する有識者会議」から小学校段階における英語教育の教科化が提案されているが、現行の中学校の英語教育の前倒し的な教育内容の実施ではなく、外国語との出会いを通した母語や言語・文化への気付き、直接的な交流を通した異文化コミュニケーション能力の育成にも寄与する「言語リテラシー教育」としての実践こそが期待されるといえよう。そうすることで、続いて行われる中学、高等学校における外国語教育にも新しい広がりが生まれてくると考えられるからである。古典的なリテラシーの概念での教育で終わらせないことがポイントといえるだろう。
(August 2014)
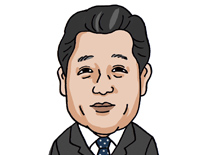
専門は英語教育、音声学、早期英語教育。日本児童英語教育学会理事、小学校英語教育学会理事。小学校~高校のデモ授業と教員研修で全国を飛び回る。講演テーマは、小中・中高連携を意識した指導、統合的な活動の開発・評価、Can-Doリスト作成の在り方、歌・ゲームを利用した英語指導など。著書多数。