金森強
文教大学 教育学部教授
専門は英語教育、音声学、早期英語教育。日本児童英語教育学会理事、小学校英語教育学会理事。小学校~高校のデモ授業と教員研修で全国を飛び回る。講演テーマは、小中・中高連携を意識した指導、統合的な活動の開発・評価、Can-Doリスト作成の在り方、歌・ゲームを利用した英語指導など。著書多数。

先頃ノーベル平和賞を受賞したパキスタン出身のマララ・ユスフザイさんのスピーチがTVのニュースで何度も流された。(2013 国連)特に最後のくだり:
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
Education is the only solution. Education first.
この言葉を重く受け止めた教育関係者は多いのではないだろうか。自分が16歳だった頃を考えると、あれだけのことを人前で堂々と語れる彼女は素晴らしいとしか言いようがない。(「大人や国連に言わされているだけ)と考える人もいるようだが・・・。)
思考・判断・表現力を育てるために、中学校や高等学校の英語の授業において、スピーチやディベートを効果的に活用することが期待されている。その指導にあたって大切になることは何だろうか。
物事を多面的に捉えることのできるクリティカル・シンキングの力を養うためにも、まずは、いろいろな話題について情報を正確に受け取ることが大切である。次のステップでは、自分の考えや情報を相手に適切に伝える能力が求められる。まずは、学習者の心が動くような受信活動(Listening, Reading)が必要であり、そこから発信活動(Speaking, Writing)へとつながっていくことが望ましいと言えそうである。
ちなみに、クリティカル・シンキングを「批判的思考」とするのは、その一面しか捉えておらず、適切な訳語ではないとする考えがある。実際、全ての事に対して「批判的」に捉えることしかできなくなってしまうと、何が正しいのかさえ分からなくなくなってしまうだろう。特に、自分の座標軸がしっかりとできていない時点であまりにも多くの情報に触れてしまうと情報に振り回されてしまうことも起こりかねない。情報と数字は簡単に操作される。
いずれにしても、どのような教育を受けるかは、一番重要であることに変わりはない。教育こそが最優先されるべきことなのである。(November 2014)
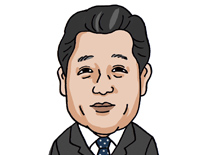
専門は英語教育、音声学、早期英語教育。日本児童英語教育学会理事、小学校英語教育学会理事。小学校~高校のデモ授業と教員研修で全国を飛び回る。講演テーマは、小中・中高連携を意識した指導、統合的な活動の開発・評価、Can-Doリスト作成の在り方、歌・ゲームを利用した英語指導など。著書多数。