竹中龍範
香川大学教育学部教授
専門は、英語教育学。特に英語教育史、英学史、英語辞書史、並びに言語文化論を研究。日本英語教育史学会会長、日本英学史学会中国・四国支部長や、文部科学省の教育研究開発企画評価会議協力者などを務める。小学校英語教育についても、研究開発学校指定校直島小学校の運営指導委員などを務める。著書・論文多数。
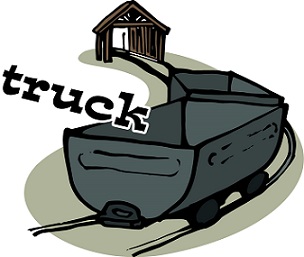
日本が開国して維新の時代を迎えた幕末・明治初期にはいろいろな誤解が生まれ、変な英語が使われていたことを前に書きました。今回は日本人が英語にどのように接したかによってその英語が日本語の中にどういう形の外来語として定着したかの例を示しましょう。
開国間もないころ、日本人の英語学習は十分に深化しておらず、耳にした英語をアルファベットで綴るだけの力がないために、聞こえたままをカナで書き留めていました。早い時期のものでは、幕末に黒船4隻を率いてやって来た提督Commodore Perryの名をオランダ語の通訳である蘭通詞は綴りそのままにコムモドール・ペルリと記しましたが、ジョン万次郎の発音によった記録にはカマダ・ペリと書かれています。
また、メリケン粉や神戸のメリケン波止場に見られる「メリケン」はAmericanから来ていますが、現在の「アメリカン」という書き方とは異なっています。これは /?mérik?n/ という発音では頭の /?/ が弱くて落ちてしまい、/mérik?n/ だけが聞き取られて、これを「メリケン」と書いたことによります。一方、同じ音が別の聞き方をされた例もありました。英語の、特にアメリカ英語の /?/ は、日本人の耳にはアともオともつかない音なので、truckという語が入ったとき、耳に聞こえたとおりに「トロッコ」と書きました。後にこの綴りを意識したことによるのか、「トラック」という表記が行われますが、トロッコとトラックは別のものをさして使い分けられています。同様のことは /i/ がイともエとも聞こえるため、stickが当初は「ステッキ」としてwalking stick、すなわち「杖」の意で日本語に入り、後に「スティック」としてアイスキャンディーの棒などを指す語として入りました。
(August 2014)

専門は、英語教育学。特に英語教育史、英学史、英語辞書史、並びに言語文化論を研究。日本英語教育史学会会長、日本英学史学会中国・四国支部長や、文部科学省の教育研究開発企画評価会議協力者などを務める。小学校英語教育についても、研究開発学校指定校直島小学校の運営指導委員などを務める。著書・論文多数。