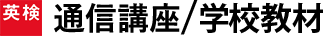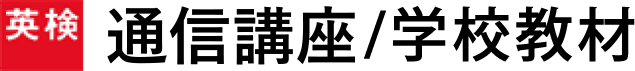- 協会TOP
- 通信講座
- コラム
- 英語の4技能を伸ばすヒント ~「非言語化」を目指す通訳トレーニングの現場から ~
- 第2回 通訳者の基礎訓練:リスニング力をつける
COLUMNS
コラム
英語の4技能を伸ばすヒント ~「非言語化」を目指す通訳トレーニングの現場から ~
第2回 通訳者の基礎訓練:リスニング力をつける
通訳者の仕事と言うと、口から発せられる言葉、つまりアウトプットの方が注目されがちです。しかし、すべてはリスニング・コンプリヘンション(listening comprehension)、つまり「聞く(listening)」と「理解する(comprehension)」ができていてこそ可能になります。では、通訳者はどのようにして英語のリスニング・コンプリヘンションの力を伸ばしているのでしょうか。今回は、2種類のトレーニングとそのメリットを紹介します。
「音声の影になってついていく」シャドーイング
まずは、シャドーイング(shadowing)をご紹介します。シャドーイングとは、リスニング対象のモデル音声を聞きつつ、少し遅れて同じ内容を口に出す練習のことを言います。その音声のイントネーションやポーズまでまねることがポイントです。ほんのちょっと遅れてオリジナルをコピーして声を出すので、まさに“shadow”(影)ですね。
シャドーイングのメリットは、まねようとすることによって英文を集中して聞くことになるため、英語のさまざまな音の特徴を確認する良い機会になることです。そのためにも、英文の文字は見ずに音だけを頼りに練習します。音に集中することよって個々の単語の発音を確認しながら、英語のリンキング※に慣れることができますし、より滑らかで意味が伝わりやすいイントネーションやポーズの取り方が徐々に身につきます。その結果として、スピーキング力アップにつながります。
※リンキング:例えば Can you... が「キャン・ユー」ではなく「キャニュー」のように音がつながる現象のこと。
では、どのような音声を使ってシャドーイングをするとよいのでしょうか。プロの通訳者ともなれば、CNNやBBCの音声でシャドーイングすることを日課にしている人もいますが、これは難易度が高めです。音声の英文は、使われている単語の9 割程度を自分が理解できることを基準にして選びましょう。また、あらかじめその内容の概要を把握しておくことも重要です。スクリプトがあれば内容を確認してからシャドーイングをしてもよいでしょう。しかし、シャドーイングのときは文字を見ずに行います(発音が文字に影響されないように、そばに置かないことをお勧めします)。
シャドーイングは音声の人物に「なりきる」ことが肝心なので、話し手の表情やジェスチャーがわかる動画を使うのも良い方法です。表情やジェスチャーがわかると、気持ちの盛り上がりや強調するべきところがよりわかりやすくなります。自分の関心がある分野のトピックを選ぶことも、楽しく続けるポイントです。
「なりきって再生」リプロダクション
次に、リプロダクション(reproduction)というトレーニングをご紹介します。リプロダクションは「再生」という意味で reproduce(再生する)という動詞が基になっていますが、教師が発する英文に従って同じ英文を繰り返す、いわゆる「リピート・アフター・ミー」に類似した、一人で行うトレーニングです。基本的な流れは以下の通りです。
- 1 素材文から適度な長さの文を選んで1文を流し、音声を止める
- 2 録音をしながら、同じ1文を言ってみる(=reproduce)
- 3 録音した英文を聞いて書き起こし、元のスクリプトと突き合わせる
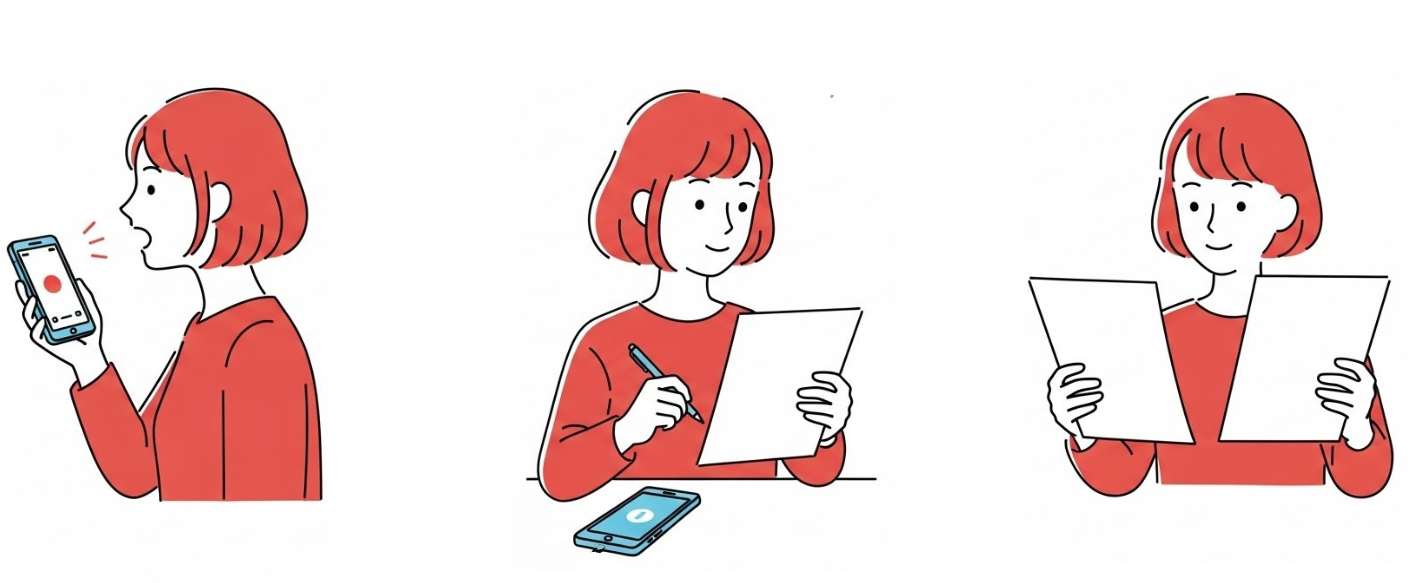
複雑で長いセンテンスであれば、5語前後の意味のある区切りで止めながら行います。シャドーイングと違い、自力で音声の再生と書き起こしを行うため、文の構成や単語を覚えていないとできないというのが難しい点です。そのため、シャドーイングと同じく自分に知識がある話題かつ単語の9割は分かる素材を探して行いましょう。
リプロダクションのメリットは、シャドーイングと同じく集中して英語を聞くことと、どのような単語がどの順番で使われているのかに注意を払うため、語彙(ごい)力や文法力が養われてより正確なリスニング力が身につく、ということです。文を区切りながらリプロダクションを行う場合は、冒頭に戻りながら英文の流れに沿って内容を理解していく思考回路を作ることにもつながります。
自分がちゃんとリプロデュースできているかを確認するには、リプロデュースをしている自分の音声を録音し、その音声と、元の音声のトランスクリプト(文字起こしをした文書)とを突き合わせる必要があります。それによりアウトプットの欠点も確認できるので、スピーキングだけでなくライティングの力を伸ばすことにもつながります。この辺りは、次回以降に取り上げます。
日本人は英語を話すと礼儀知らずになる?
英語は日本語に比べて尊敬語や謙譲語がなく人間関係がフラットになるから話し方に気を遣わなくていい。私がかつてそうであったように、そのようなイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、英語にも気遣いを表す表現が存在します。それを知らずに礼儀がない話し方になってしまう日本人は少なくありません。「日本人は礼儀正しいはずなのに…」と思われるのは残念ですね。
そのような状況を避けるために、基本のpleaseを大切にしましょう。例えば、飛行機で客室乗務員に食事について “Chicken or fish?” と聞かれたら、必ずplease を文末につけて “Chicken, please.” などと言いましょう。英語圏では、子どものころから「〜がほしい」には pleaseをつけるよう教え込まれます。厳しく言えば、これができないと幼稚園生以下と思われてしまうのです。一方で、「〜してください」と依頼するときに気を付けたいのは、命令文に pleaseをつける言い方です。命令文はあくまでも「命令」なので、例えば “Please finish the work by this Friday.”(今週金曜日までにその仕事を終わらせてください)は、いわゆる「上から目線」の発言に聞こえます。丁寧に依頼する場合は、Would you...? やCould you...? を使うのが一般的です。
森住史 (もりずみ ふみ)氏
成蹊大学文学部英語英米文学科教授(社会言語学・通訳学)、サイマル・アカデミー通訳者養成コース講師
国際基督教大学教養学部語学科卒、国際基督教大学大学院教育学研究科博士課程前期・後期修了・博士号取得(英語教授法)。ロンドン大学とエディンバラ大学にそれぞれ1年間留学。
NHKラジオ講座「入門ビジネス英語」(2011年度後期)の講師として、英文Eメールの書き方についてのテキストの執筆にも携わる。2012年から継続執筆中のAsahi Weeklyのコラム『森住 史の英語のアレコレQ&A』では、受験英文法の確認から気を付けたいエチケットまで幅広く解説。英語を使う際の「コンテクスト」を常に重視。
通信講座『12の鉄則で学ぶ スタート英文Eメール』『英語発想で書ける! 英文Eメール中級講座』の監修・執筆者。