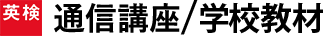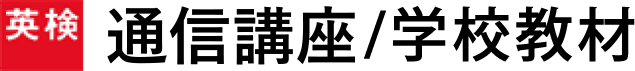- 協会TOP
- 通信講座
- コラム
- 英語の4技能を伸ばすヒント ~「非言語化」を目指す通訳トレーニングの現場から ~
- 第1回 「非言語化」で日本語・英語の縛りから抜け出そう
COLUMNS
コラム
英語の4技能を伸ばすヒント ~「非言語化」を目指す通訳トレーニングの現場から ~
第1回 「非言語化」で日本語・英語の縛りから抜け出そう
英語の4技能をバランスよく伸ばすにはどうすればいいかと悩んでいる学習者は多いのではないでしょうか。本コラムでは、通信講座『12の鉄則で学ぶ スタート英文Eメール』『英語発想で書ける! 英文Eメール中級講座』の監修・執筆者で通訳者の森住史先生が、通訳者が行う基礎のトレーニング法を解説します。英語の4技能を伸ばすためのヒントが満載です。
具体的なトレーニングの紹介をする前に、今回は通訳の現場で使われる「非言語化」という理論をご紹介します。
通訳者や翻訳者が通訳や翻訳をするとき、「日本語→英語」「英語→日本語」という単純な変換作業をしているように思えるかもしれませんが、実際は少し違います。通訳や翻訳では、聞き手・読み手が聞いた・読んだオリジナル言語の言語体系からいったん離れ、話者や書き手が伝えたいメッセージを頭の中で解釈し、それを別言語に落とし込んでいる、というのがより近いプロセスです。

このプロセスで重要なのは、オリジナル言語の表現や文構造に縛られず、通訳者の頭の中で抽象的なものをビジュアル化し具体的なものにしたり、あるいはその逆をしたりしながら発信者の伝えたいメッセージを捉え直すという部分です。通訳の世界ではこれを「非言語化」(あるいは「脱言語化」)と呼びます。これは会議通訳者・通訳学者のフランス人セレスコヴィッチが提唱した考え方で、通訳者が通訳をするときに、意味の理解と伝達のプロセスの一環として行っているものです。
具体的な例を挙げて見ていきましょう。例えば、日本文化をよく知らない外国人を花見に誘う場面を考えてみます。日本語の「花見」を漢字のままflower viewingと訳したとします。日本人なら、「花見」と聞いたら桜がたくさん咲いている公園をそぞろ歩きする大勢の人たちや、その人たちが食べ物や飲み物を持って歩いていたり、車座になって宴会をしていたりするイメージがパッと浮かぶはずです。しかし、flower viewing にはそのイメージはありません。flower には桜以外の花も含まれますし、viewの意味には飲食の要素はありませんから、“Let’s go flower viewing.”と言っても日本人が一般的に考える「花見に誘う」メッセージにはなりません。そこで、「非言語化」が重要になります。日本文化を知らない相手、という情報を念頭に訳出すると、次のような言い方が可能です。
“Would you like to join us for a picnic? We plan to enjoy the cherry blossom view and enjoy eating and drinking.” (一緒にピクニックに行きませんか。桜を見ながら食べたり飲んだりしようと思っているんです)
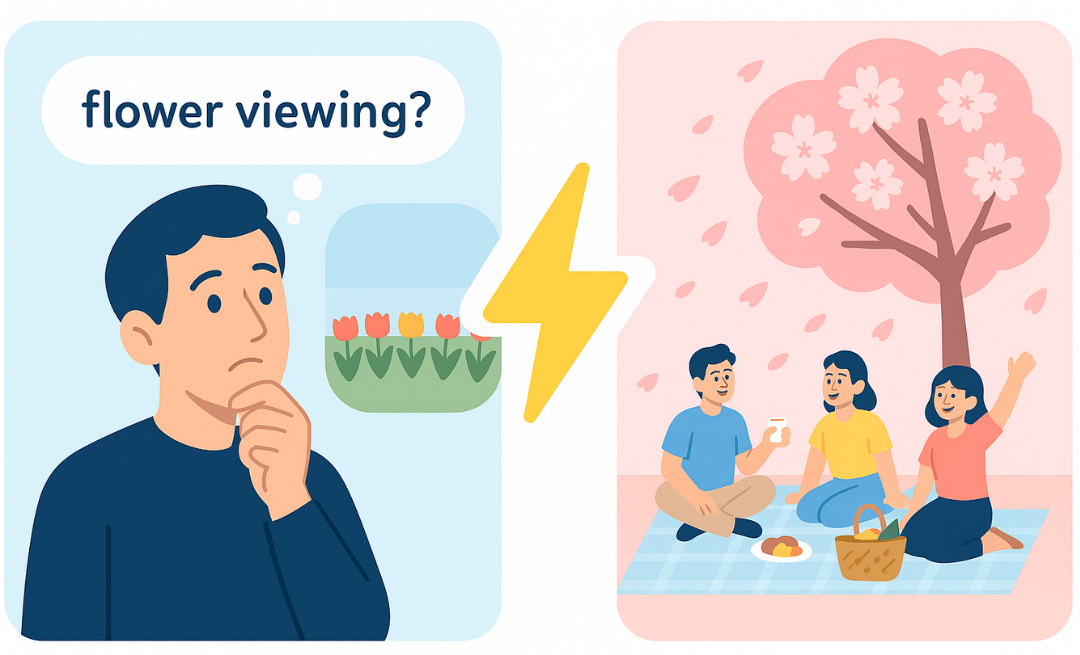
以上のことを念頭に置き、ビジネスで英語を使うシーンに置き換えてみましょう。例えば、日本語のビジネスメールは社内の人同士でも「お疲れさまです。〇〇部の××です」のようにあいさつで始まることが多いですね。しかし、ビジネス英文メールではよく知っている者同士ではあいさつはせず、用件から始めます。日本語のメールでは決まり文句を使ったあいさつで書き始めることが「相手への気遣い」を表しますが、英文メールではシンプルに書くのが「相手への気遣い」であるため、あいさつは省くのが普通なのです。これも日本語から英語に訳出するときの「非言語化」の一つであると言えるでしょう。
英語と私:私が英語の勉強にハマったわけ
私が英語に初めて触れたのは小学校高学年のときで、たまたま友人にくっついて行った英会話教室でした。日本語とまるっきり異なる音が聞こえてくることに驚き、カセットテープでの録音を自分で繰り返すようになりました。次第に自分の口からいつもと違う音が出せるようになるのが楽しくて仕方なかったのです。
その後は、いわゆる学校英語の学習が中心になりましたが、三人称単数が主語のときには動詞にsがつく、という文法ルールも、パズル感覚で楽しんでいました。そして10代の多感な時期になり、「相手が親でも先生でも you で良いなんて、対等に話しやすそうだ」と思ったことから、英語を話す人たちの文化や価値観に興味を持ち始めました。日本語では、相手を「〇〇先生」などと呼ぶ時点で自分を「下」の立場に置くことになって、話をするにおいて不利なんじゃないか、などと思ったのです。もちろん、英語でも上下関係を表す言葉遣いがあることを今では理解していますが、当時は日本語と英語の同じ部分や異なる部分を面白く感じていました。
このようにして、次第に英語の勉強にハマっていったのです。
森住史 (もりずみ ふみ)氏
成蹊大学文学部英語英米文学科教授(社会言語学・通訳学)、サイマル・アカデミー通訳者養成コース講師
国際基督教大学教養学部語学科卒、国際基督教大学大学院教育学研究科博士課程前期・後期修了・博士号取得(英語教授法)。ロンドン大学とエディンバラ大学にそれぞれ1年間留学。
NHKラジオ講座「入門ビジネス英語」(2011年度後期)の講師として、英文Eメールの書き方についてのテキストの執筆にも携わる。2012年から継続執筆中のAsahi Weeklyのコラム『森住 史の英語のアレコレQ&A』では、受験英文法の確認から気を付けたいエチケットまで幅広く解説。英語を使う際の「コンテクスト」を常に重視。
通信講座『12の鉄則で学ぶ スタート英文Eメール』『英語発想で書ける! 英文Eメール中級講座』の監修・執筆者。